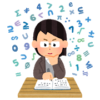【電験三種法規科目】出題率の高い「重要数値」を正確に記憶する覚え方
電験三種の法規科目の点数をあげる方法の一つが、
出題率の高い「数値」を正確に記憶する
です。
電験三種試験には理論、機械、電力、法規の4科目あり、
中でも法規科目は、暗記しておかなければ解答することができない問題が多く出題されます。
そのため、法規科目は4科目の中でも勉強に時間がかかり点数が取りづらい科目と言われています。
そんな法規科目のポイントが絶対に抑えておきたい数値!です。
この記事で紹介する「数値」は、電験三種の試験を7回も受験し続けた私が特に重要と感じたものです。
100%出題されるわけではありませんが、
重要な数値が頭に入っているか、入っていないかで試験当日の精神状態にかなり差が出ます。
合格した年は、「これだけ知識を詰め込んできたのだから絶対に大丈夫!」という精神状態で試験に臨むことができました。
これから受験する方、受験し続けているけどなかなか合格できない方は、
是非この記事で紹介されている「数値」を頭に入れて自信につなげてみてください。
目次
電圧の区分
| 交流 | 直流 | |
| 低圧 | 600V以下 | 750V以下 |
| 高圧 | 低圧を超え7000V以下 | 低圧を超え7000V以下 |
| 特別高圧 | 7000Vを超えるもの | 7000Vを超えるもの |
低圧の中でも交流と直流で「数値」が異なります。
600Vと750Vの違いを問う問題はよく出題されるのでしっかり覚えておきましょう。
いろんな練習問題をやっていると高圧の部分に記載されている、
「以下」「超えるもの」の違いが問われる問題も出題率が高いです。
低圧と高圧両方まとめて覚えてしまいましょう。
接地抵抗値
| A種 | 10Ω以下 | 10Ω以下 |
| B種 | 600/Ig | 遮断時間1秒以下 |
| 300/Ig | 1秒を超え2秒以下 | |
| 150/Ig | 上記以外 | |
| C種 | 10Ω以下 | 0.5秒以内に電路を自動遮断できる場合は500Ω以下 |
| D種 | 100Ω以下 | 0.5秒以内に電路を自動遮断できる場合は500Ω以下 |
接地抵抗の問題はかなり高い確率で出題されます。
参考書にはもっと詳しい説明が記載されていますが、最低でも上記で紹介した「数値」はすらすら出てくるようににしましょう。
特にB種接地抵抗値の使い分けをよく理解しておく必要があります。
なぜなら、B種接地抵抗値の使い分けは計算問題でよく出題され、
3種類全ての使い分けパターンで出題されるからです。
例えば、
- 設備されている遮断器の遮断時間は1秒以下です。このときのB種接地抵抗値は?
- 設備されている遮断器の遮断時間は3秒を超えます。このときのB種接地抵抗値は?
というように、文言がちょっと変わっただけで「600/Ig」を使うのか、「150/Ig」を使うのか、
計算方法が変わってきます。

豆父ちゃん
いろんな電線やケーブルの太さ・引張強さ
接地線
| 接地抵抗 | 太さ | 引張強さ |
| A種 | 2.6mm | 1.04kN |
| B種 | 4mm | 2.46kN |
| C種 | 1.6mm | 0.39kN |
| D種 | 1.6mm | 0.39kN |
私は語呂合わせで覚えました。
接地線の「太さ」「引張強さ」を覚える語呂合わせ
えーニロテンフォー、びーフォーニシロ、しーでぃーイチロクサンキュウー
A種2.6mm1.04kN、B種4mm2.46kN、C種D種1.6mm0.39kN
得に意味はありませんが、この語呂のおかげでいつでも思い出すことができます。
架空電線路
300V以下の低圧架空電線路
絶縁電線(その他)・・・引張強さ2.3kN
絶縁電線(硬銅線)・・・直径2.6mm
多心型電線(硬銅線)・・・直径3.2mm
多心型電線(その他)・・・引張強さ3.44kN
300V以下の低圧架空電線路の「太さ」「引張強さ」を覚える語呂合わせ
ニーサンニロクなのいない、そうだろサニーサンヨー
絶縁電線、多心型電線、硬銅線、その他の順番さえ覚えておけば、
正確な「数値」を思い出すことができます。
300V超過の低圧及び高圧架空電線路
多心型電線(硬銅線)・・・直径3.2mm
市街地(硬銅線)・・・直径5mm
市街地(その他)・・・引張強さ8.01kN
市街地(硬銅線)・・・直径4mm
市街地(その他)・・・引張強さ5.26kN
300V超過の低圧及び高圧架空電線路の「太さ」「引張強さ」を覚える語呂合わせ
ゴッパーオイオイ太すぎだ、シゴニロクなことはない
架空ケーブルを支持するちょう架線
引張強さ5.93kN以上のもの、または断面積22mm2以上の亜鉛メッキ鉄より線であること
架空ケーブルを支持するちょう架線の「太さ」「引張強さ」を覚える語呂合わせ
ケーブル引くの、ゴクウサンニーお願いする
低圧架空引込電線
引張強さ2.3kN以上のもの、または直径2.6mm以上の硬銅線、ただし径間が15m以下のとき引張強さ1.38kN以上のもの、または直径2mm以上の硬銅線とする。
低圧架空引込電線の「太さ」「引張強さ」を覚える語呂合わせ
ニーサンニロクなのいない、イゴイーサンハントニは気をつけて
高圧架空引込電線
高圧・特別高圧絶縁電引込線は直径5mm以上または引張強さ8.01kN以上の硬銅線
高圧架空引込電線の「太さ」「引張強さ」を覚える語呂合わせ
ゴッパーオイおい太すぎだ
試験によく出題される電線の高さ
架空電線の高さ
| 低圧架空電線 | 高圧架空電線 | |
| 鉄道または軌道を横断する場合 | 5.5m | 5.5m |
| 道路を横断する場合 | 6m | 6m |
| 上記以外 | 5m | 5m |
| 横断歩道橋の上に施設する場合 | 3m | 3.5m |
架空電線の高さの語呂合わせ
(鉄道の外歩け、低圧はゴーゴー、ロクゴーさん、高圧はちょっと多めに)
全く語呂合わせになっていませんが、私はこのように覚えました。
低圧架空引込線の高さ
| その他の場合 | 技術上やむを得ない場合 | |
| 鉄道または軌道を横断する場合 | 5.5m | |
| 道路を横断する場合 | 5m | 3m |
| 上記以外 | 4m | 2.5m |
| 横断歩道橋の上に施設する場合 | 3m |
低圧架空引込線の高さの語呂合わせ
鉄道の外歩け、5.5→5→4→3→3→3.5
順番だけ語呂合わせで覚えて、数値はどんどん減っていくと覚えました。
高圧架空引込線の高さ
| その他の場合 | 技術上やむを得ない場合 | |
| 鉄道または軌道を横断する場合 | 5.5m | |
| 道路を横断する場合 | 6m(低圧の+1m) | |
| 上記以外 | 5m(低圧の+1m) | |
| 横断歩道橋の上に施設する場合 | 3.5m(低圧の+0.5m) |
高圧架空引込線の高さの語呂合わせ
鉄道の外歩け、5.5→6→5→3.5
順番だけ語呂合わせで覚えて、数値は低圧と比較して覚えました。
絶縁抵抗測定値
電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器または過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに表に掲げる電路の使用電圧の区分に応じそれぞれ表に掲げる絶縁抵抗値以上でなければならない。
なお絶縁抵抗の測定が困難な場合は、同電路区分ごとの漏洩電流が1mA以下であればよい。
| 電路の使用電圧の区分 | 絶縁抵抗[MΩ] |
| 300V以下かつ対地電圧150V以下 | 0.1 |
| 300V以下かつ対上記以外 | 0.2 |
| 300Vを超えるもの | 0.4 |
絶縁抵抗値の問題はかなり出題率が高いです。
上記で印をついている箇所は特に覚えた方がいいでしょう。
問題の選択肢として
使用電圧→対地電圧・線間電圧・定格電圧
過電流遮断器→配線用遮断器・低圧ヒューズ
1mA→0.5mA・1.5mA
と出題されることがあります。
似たような数字や語句が選択肢にあっても迷わず回答できるようしっかり覚えましょう。
低圧電路の過電流遮断器の動作特性
ヒューズ
- 定格電流の1.1倍の電流に耐えること
- 定格電流の1.6倍の電流を通じた場合にT2の時間内に溶断すること
- 定格電流の2倍の電流を通じた場合にT1の時間内に溶断すること
低圧ヒューズの溶断特性
| 定格電流の区分 | T2 | T1 |
| 30A以下 | 60分以下 | 2分以下 |
| 30Aを超え60A以下 | 60分以下 | 4分以下 |
| 60Aを超え100A以下 | 120分以下 | 6分以下 |
配線用遮断器
- 定格電流の1倍の電流で自動的動作しないこと
- 定格電流の1.25倍の電流を通じた場合にT2の時間内に溶断すること
- 定格電流の2倍の電流を通じた場合にT1の時間内に溶断すること
配線用遮断器の遮断特性
| 定格電流の区分 | T2 | T1 |
| 30A以下 | 60分以下 | 2分以下 |
| 30Aを超え50A以下 | 60分以下 | 4分以下 |
| 50Aを超え100A以下 | 120分以下 | 6分以下 |
定格電流のそれぞれの倍数を覚えましょう。
よく参考書では溶断特性の一覧表は10行くらい紹介されていますが、私は最初の3行だけ覚えれば十分だと思います。
- T2が60分以下→120分以下になる変更となるときの定格電流の区分
- 低圧ヒューズと配線用遮断器を比較したとき、溶断特性の一覧表の異なる箇所
以上2点はよく試験で出題されます。

豆父ちゃん
高圧電路の過電流遮断器の動作特性
包装ヒューズ
定格電流の1.3倍の電流に耐え、かつ2倍の電流で120分以内に溶断するもの
非包装ヒューズ
定格電流の1.25倍の電流に耐え、かつ2倍の電流で2分以内に溶断するもの
低圧電路と高圧電路の過電流遮断器の動作特性はよく試験に出題されます。
倍率や時間が似たようなものが多いので、しっかり区別して覚えましょう。
電験三種法規科目の勉強は時間が大事
法規科目の勉強は短い時間でいいので毎日行うことが重要です。
私が合格した年は毎日必ず15分程度法規科目の勉強をしていました。
全然気分が乗らない日でもこの記事で紹介している重要な数値の復習だけは欠かさず行っていると、
数値が頭に定着し10分程度の時間で復習できるようになってくるはずです。
この記事で紹介した絶対に抑えておきたい数字は毎年2問〜3問は出題されます。
この数字が自然にすらすらイメージできれば、自信をもって試験に臨むことができ精神的にも余裕を持てるはずです。
覚えることが多くて大変かと思いますが、諦めずに頑張りましょう。
下記の記事では、電験三種の合格に必要な勉強時間について私の体験談を詳しくご紹介しています。
電験三種は徹夜付けで合格できるような簡単な試験ではありません。
しかし、毎日継続して勉強を続ければいつかは合格できるレベルの試験でもあります。

豆父ちゃん